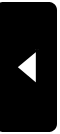2007年09月03日
親孝行する人は、世を乱さず
親孝行する人は、世を乱さず
「有子曰く、其の人と為りや、孝弟にして上を犯すを好む者は鮮(すく)なし。上を犯す好まずして乱を作(な)すを好む者は未だ之にあらざるなり。君子は本を務む、本立ちて道生ず。孝弟なる者は、それ仁を為すのもとか。」
(意味)
有先生が言われた「その人柄が、家に在っては、親に孝行を尽くし、兄や姉に従順であるような者で、長上にさからう者は少ない。長上に好んでさからわない者で、世の中を乱すことを好むような者はない。
何ごともまず本に務めることが大事である。本が立てば、進むべき道は自ずから開けるものだ。従って孝弟は仁徳を成し遂げる本であかろうか」
(感想)
「修身、斉家、治国、平天下」が、大人の思考の領域ですが、一番難しいのは、自分自身の向上心を維持し続けること、次に大事なのが家庭内の平安で、その中でも重要なのが孝行と思います。身近だからこそ、敬う心を忘れがちですが、できこと、言葉使いに心がけることから、始めて行くと自分も子ども(孫)たちも変って行くように思います。
「有子曰く、其の人と為りや、孝弟にして上を犯すを好む者は鮮(すく)なし。上を犯す好まずして乱を作(な)すを好む者は未だ之にあらざるなり。君子は本を務む、本立ちて道生ず。孝弟なる者は、それ仁を為すのもとか。」
(意味)
有先生が言われた「その人柄が、家に在っては、親に孝行を尽くし、兄や姉に従順であるような者で、長上にさからう者は少ない。長上に好んでさからわない者で、世の中を乱すことを好むような者はない。
何ごともまず本に務めることが大事である。本が立てば、進むべき道は自ずから開けるものだ。従って孝弟は仁徳を成し遂げる本であかろうか」
(感想)
「修身、斉家、治国、平天下」が、大人の思考の領域ですが、一番難しいのは、自分自身の向上心を維持し続けること、次に大事なのが家庭内の平安で、その中でも重要なのが孝行と思います。身近だからこそ、敬う心を忘れがちですが、できこと、言葉使いに心がけることから、始めて行くと自分も子ども(孫)たちも変って行くように思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
01:08
│Comments(0)
2007年09月03日
巧言令色鮮(すく)なし仁
最近、政治家の不祥事が続いていますが、学而第一の第二話に、次に一説があります。
「子曰わく、巧言令色鮮(すく)なし仁。」
(孔子曰く)「ことさらに言葉を飾り、顔色をよくする者は、仁の心が乏しいものだよ」
*仁:相手を思いやる心、哀れみ
要は、自分本位で相手の思いを無視して、自分の主張(我)を通したり、その場をつくろってしまい、問題を先送りにしてしまったりします。
「子曰わく、巧言令色鮮(すく)なし仁。」
(孔子曰く)「ことさらに言葉を飾り、顔色をよくする者は、仁の心が乏しいものだよ」
*仁:相手を思いやる心、哀れみ
要は、自分本位で相手の思いを無視して、自分の主張(我)を通したり、その場をつくろってしまい、問題を先送りにしてしまったりします。
Posted by ノグチ(noguchi) at
01:07
│Comments(0)
2007年09月03日
曹子曰く、吾日に吾が身を三省す
「曹子曰く、吾日に吾が身を三省す」
(意味)
(曹先生が言われた)、私は毎日、自分をたびたびかえりみて、良くないことをはぶいている。人の為を思うて、真心からやったかどうか。友達と交わってうそいつわりはなかったか。まだ習得していないことを人に教えるようなことはなかったか。
一日三省の言葉は、ここから出てたと言われています。また出版社の「三省堂」の語源と聞きました。時間を見つけて、自分を省みるゆとりを持ちたいものです。
(意味)
(曹先生が言われた)、私は毎日、自分をたびたびかえりみて、良くないことをはぶいている。人の為を思うて、真心からやったかどうか。友達と交わってうそいつわりはなかったか。まだ習得していないことを人に教えるようなことはなかったか。
一日三省の言葉は、ここから出てたと言われています。また出版社の「三省堂」の語源と聞きました。時間を見つけて、自分を省みるゆとりを持ちたいものです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
01:07
│Comments(0)
2007年09月03日
「学而第一」 朋(とも)遠方より来る有り、亦楽しからずや。
「学而第一」 ~朋(とも)遠方より来る有り、亦楽しからずや。~
「子曰わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしからずや。朋(とも)遠方より来る有り、亦楽しからずや。人知らずしてうらみず、亦君子ならずや。」
大人だったら、どこかで一度は聞いている言葉と思います。最近の小中では聞けない言葉と思います。
今日改めてその意味を聞くと、「これは、早くから意味は分からないまでも、この文章に慣れさせることが大事」と思いました。
上記の意味は、次のようなものです。
(孔子曰く)「聖賢の道を学んで、時に応じてこれを実践し、その真意を自ら会得することができるのは、なんと喜ばしいことではないか。共に道を学ぼうとして、思いがけなく遠くから同志がやって来るのは、なんと楽しいことではないか。
だが人が自分の存在を認めてくれなくても、怨むことなく、自ら為すべきことを努めてやまない人、なんと立派な人物ではないか。」
「子曰わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしからずや。朋(とも)遠方より来る有り、亦楽しからずや。人知らずしてうらみず、亦君子ならずや。」
大人だったら、どこかで一度は聞いている言葉と思います。最近の小中では聞けない言葉と思います。
今日改めてその意味を聞くと、「これは、早くから意味は分からないまでも、この文章に慣れさせることが大事」と思いました。
上記の意味は、次のようなものです。
(孔子曰く)「聖賢の道を学んで、時に応じてこれを実践し、その真意を自ら会得することができるのは、なんと喜ばしいことではないか。共に道を学ぼうとして、思いがけなく遠くから同志がやって来るのは、なんと楽しいことではないか。
だが人が自分の存在を認めてくれなくても、怨むことなく、自ら為すべきことを努めてやまない人、なんと立派な人物ではないか。」
Posted by ノグチ(noguchi) at
01:06
│Comments(0)
2007年09月03日
宇土親子論語教室開講式
宇土親子論語教室開講式
~「一灯照隅」の気持ちで、参加し学ぶ会~
・親子論語教室開講
さて、その大雨の七夕の日に、地元の宇土市に、「親子論語教室」が開講されました。昨年夏から、話が持ち上がり、準備を進めて来て、本日は熊本市の東洋倫理研究会の塾長の筑紫凡三先生の講演で始まりました。
まだまだ、こどもの参加が12名の小さな論語教室ですが、皆さんも一度は耳にしてことのある
「子曰(のたま)わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしまらずや。朋遠方より来る有り、亦楽しからずや。人知らずしてうらみず、亦君子ならずや。・・・・」
とあります。孔子の教えを、門人たちが議論しならがら、公正に伝えようと、孔子の語った言葉を残したの「論語」の説明から、2500年前に、人の道「礼」を教えた、中国最初の学校「教養学習所」と説明されると、先駆者の偉業に更に関心を持ちます。
子供たちは、むずかしい言葉に、さわりに部分では、興味がなく集中注力が薄れて、うろうろしたのですが、論語の最初のくだりを、大人と一緒に朗読して時は、同じように声に出し、合唱していました。
江戸期に行われた、素読と言う方法で、論語の言葉を暗記し、人生の節目節目で、振り返り学び直したと知りました。人生の教科書とも言われる「論語」を学ぶ風景を「子供たちの記憶」の残すことに意味があるのではと思います。
私は、中国古典輪読会に参加して出会った、幕末-明治の陽明学者の山田方谷先哲は、4歳から家を離れ33歳まで遊学(学問をして渡り歩く)して、地元岡山の中部に在った「備中松山藩」で仕事をするのですが、その生き方に大きく惹かれました。
山田方谷のエピソードの一つに、10代後半の青年たちと一緒に机を並べる9歳の方谷少年に、訪問した大人がからかうつもりで、「君は何のために勉強してるか」の質問に対して、方谷は、「治国平天下」と即答し、質問した訪問者が腰を抜かしたと言われています。若き天才。山田方谷の逸話は、色々ありますが、鉄は熱いうちに打ての訓示通り、方谷少年は晩年まで貫いた「至誠」の人生を見るに、とても教育が大事と感じます。
最近、親を殺す、子を殺すの悲惨を事件を見るに、日本の孝行、慈愛の「美しい心」は、どこへ行ったのでしょうと疑いたくなります。日本人は、その出来事から、「自身の歴史」を検証し、次の時代を改善するために行動が始まっていると思います。
その一つが、「宇土親子論語教室」につながっていると思います。私も準備に関わって来て、自分自身が自分の子に「範を示す」大切さを反省しつつ、自分も学ぶことの必要性を感じています。
毎月第一土曜日、午前10時~11時30分まで、講話や、論語カルタ、論語百人一首などの遊びもしつつ、子供たちの記憶の中に、「聖人の言葉を残す」ことを続けて行きたいと思います。
「子曰(のたま)わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしまらずや。」
の言葉が、色々なところで聴けるようになると良いなと思います。孔子の教え「孝行」の思いやりの心「仁」の精神が、地元の宇土市から、発信して行ければと思っています。
私も事務局のスタッフの一人として、「一灯照隅」の気持ちで、参加し学んで行きたいと思っています。
今日は、熊本、九州の大雨の状況と、地元の宇土市に「親子路論語教室」が始まった話をしました。来週もまだ大雨の心配はありますが、皆様のところも被害が出ないように願っています。本当に、お見舞いメールありがとうございました。
~「一灯照隅」の気持ちで、参加し学ぶ会~
・親子論語教室開講
さて、その大雨の七夕の日に、地元の宇土市に、「親子論語教室」が開講されました。昨年夏から、話が持ち上がり、準備を進めて来て、本日は熊本市の東洋倫理研究会の塾長の筑紫凡三先生の講演で始まりました。
まだまだ、こどもの参加が12名の小さな論語教室ですが、皆さんも一度は耳にしてことのある
「子曰(のたま)わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしまらずや。朋遠方より来る有り、亦楽しからずや。人知らずしてうらみず、亦君子ならずや。・・・・」
とあります。孔子の教えを、門人たちが議論しならがら、公正に伝えようと、孔子の語った言葉を残したの「論語」の説明から、2500年前に、人の道「礼」を教えた、中国最初の学校「教養学習所」と説明されると、先駆者の偉業に更に関心を持ちます。
子供たちは、むずかしい言葉に、さわりに部分では、興味がなく集中注力が薄れて、うろうろしたのですが、論語の最初のくだりを、大人と一緒に朗読して時は、同じように声に出し、合唱していました。
江戸期に行われた、素読と言う方法で、論語の言葉を暗記し、人生の節目節目で、振り返り学び直したと知りました。人生の教科書とも言われる「論語」を学ぶ風景を「子供たちの記憶」の残すことに意味があるのではと思います。
私は、中国古典輪読会に参加して出会った、幕末-明治の陽明学者の山田方谷先哲は、4歳から家を離れ33歳まで遊学(学問をして渡り歩く)して、地元岡山の中部に在った「備中松山藩」で仕事をするのですが、その生き方に大きく惹かれました。
山田方谷のエピソードの一つに、10代後半の青年たちと一緒に机を並べる9歳の方谷少年に、訪問した大人がからかうつもりで、「君は何のために勉強してるか」の質問に対して、方谷は、「治国平天下」と即答し、質問した訪問者が腰を抜かしたと言われています。若き天才。山田方谷の逸話は、色々ありますが、鉄は熱いうちに打ての訓示通り、方谷少年は晩年まで貫いた「至誠」の人生を見るに、とても教育が大事と感じます。
最近、親を殺す、子を殺すの悲惨を事件を見るに、日本の孝行、慈愛の「美しい心」は、どこへ行ったのでしょうと疑いたくなります。日本人は、その出来事から、「自身の歴史」を検証し、次の時代を改善するために行動が始まっていると思います。
その一つが、「宇土親子論語教室」につながっていると思います。私も準備に関わって来て、自分自身が自分の子に「範を示す」大切さを反省しつつ、自分も学ぶことの必要性を感じています。
毎月第一土曜日、午前10時~11時30分まで、講話や、論語カルタ、論語百人一首などの遊びもしつつ、子供たちの記憶の中に、「聖人の言葉を残す」ことを続けて行きたいと思います。
「子曰(のたま)わく学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしまらずや。」
の言葉が、色々なところで聴けるようになると良いなと思います。孔子の教え「孝行」の思いやりの心「仁」の精神が、地元の宇土市から、発信して行ければと思っています。
私も事務局のスタッフの一人として、「一灯照隅」の気持ちで、参加し学んで行きたいと思っています。
今日は、熊本、九州の大雨の状況と、地元の宇土市に「親子路論語教室」が始まった話をしました。来週もまだ大雨の心配はありますが、皆様のところも被害が出ないように願っています。本当に、お見舞いメールありがとうございました。
Posted by ノグチ(noguchi) at
01:02
│Comments(0)