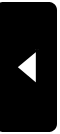2013年08月10日
不祥事の多い時代だが、無欲な人ほど、正義の上に立つと強いものである。
不祥事の多い時代だが、無欲な人ほど、正義の上に立つと強いものである。
おはようございます。今日も蒸し暑い朝です。東北では、とんでもない豪雨、被災された方の早い復旧と復興を願います。
さて、地位や名誉を好まない人ほど扱いにくいものはないと、何かの本で読みました。お礼しようにも「要らない」の一言、この世の中、ごますり、上げ足、不正、賄賂、等々が多いようだ。自分よがりの言動が、不祥事を頻発させている。
新聞では、諸官庁のトップが、部下の不祥事で頭を下げることの多いこと、熊本市は飲み会の場に、車で行かない宣言(規約)を決めたとか? 子どもではあるまいし、情けないルールを公表しなければいけないモラルの低下に、社会人の気質が問われている。
君子を喜ばせるの難しい。不正やごますりなど退け、賄賂も喜ばない。
これに対し、小人(私利私欲の多い人)を喜ばせるのは簡単。私利私欲しか考えていないため、ごますりや贈り物をすればたやすく喜ぶ。ただし、小人には人を愛する心がないため、仕えるのが難しい。
渋沢栄一は、商業を営む目的は、「私利私欲ではなく、公利公益だ」と強調している。そもそも、商売は世の中の困りごとを解決することが目的だったが、目的よりも金が先になり、振り込め詐欺のような、相手のことは知ったことではない、私利私欲の輩が出て来た。
自分の携わる仕事が、公益に沿ったものか? ちょっと考える。
世の中の困りごとを解決する仕事に関係し、その見返りで生かされていることに感謝するような仕事をできれば、幸せ者のように思います。「金が先にあり」ではなく、私欲を限りなく公益に近づける志向を持って、自分に与えられた仕事に取り組めば、違った社会の見方が出てくると思います。
おはようございます。今日も蒸し暑い朝です。東北では、とんでもない豪雨、被災された方の早い復旧と復興を願います。
さて、地位や名誉を好まない人ほど扱いにくいものはないと、何かの本で読みました。お礼しようにも「要らない」の一言、この世の中、ごますり、上げ足、不正、賄賂、等々が多いようだ。自分よがりの言動が、不祥事を頻発させている。
新聞では、諸官庁のトップが、部下の不祥事で頭を下げることの多いこと、熊本市は飲み会の場に、車で行かない宣言(規約)を決めたとか? 子どもではあるまいし、情けないルールを公表しなければいけないモラルの低下に、社会人の気質が問われている。
君子を喜ばせるの難しい。不正やごますりなど退け、賄賂も喜ばない。
これに対し、小人(私利私欲の多い人)を喜ばせるのは簡単。私利私欲しか考えていないため、ごますりや贈り物をすればたやすく喜ぶ。ただし、小人には人を愛する心がないため、仕えるのが難しい。
渋沢栄一は、商業を営む目的は、「私利私欲ではなく、公利公益だ」と強調している。そもそも、商売は世の中の困りごとを解決することが目的だったが、目的よりも金が先になり、振り込め詐欺のような、相手のことは知ったことではない、私利私欲の輩が出て来た。
自分の携わる仕事が、公益に沿ったものか? ちょっと考える。
世の中の困りごとを解決する仕事に関係し、その見返りで生かされていることに感謝するような仕事をできれば、幸せ者のように思います。「金が先にあり」ではなく、私欲を限りなく公益に近づける志向を持って、自分に与えられた仕事に取り組めば、違った社会の見方が出てくると思います。
2013年08月09日
山口県立図書館の幕末維新関連図書に多さは西日本一では!
山口県立図書館の幕末維新関連図書に多さは西日本一では!
朝から山口県立図書館で、幕末維新に関する本や資料を見ていて、少々くたびれて休憩タイムです。さて、流石に山口県と感銘を受けました。明治の新政府側だけの資料だけでなく、旧幕府側からみた検証本、小説も含め、蔵書の多さに驚きます。
ただ、昨日の防府市立図書館にあった『江戸の旅人吉田松陰』(海原徹著)の本はありませんでした。高杉晋作の横井小楠と佐久間象山の批評の言葉の本はありました。地域地域で、市民の関心が異なるので、山口県内でも、蔵書に変化があると思いました。
下関市立図書館と防府市立図書館は、最新鋭の建物でしたが、山口県立図書館は、昭和の大建築家の故前川國男氏の設計で、緑の中で落ち着いて色合いの建物でした。設備等は、最新の検索機器類があり、県営の図書館の力の入れ方が違うと思いました。
せっかくと思い、地方自治、特に地方議会について分析研究をした本はないか調べましたが、熊本同様に皆無です。市民の関心は、選挙だけで議会活動には、まだまだ無関心のようです。これからは地方の時代と言われて久しいですが、市民の自治への関心力が、選挙だけではなかなか自立へ向けた動きにつながりません。
高杉晋作が、藩政の主導権を握るために、決起し行動したように、現代人は、地元自治の現場へ出向き、自分の目で確認し、意見を言い、要求をアピールする動きをやらなければ、自治改革は実現しない。特に地方議会への関心が必要と思います。
後、1時間ほど資料を調査し、ぼちぼち九州へ帰ります。
朝から山口県立図書館で、幕末維新に関する本や資料を見ていて、少々くたびれて休憩タイムです。さて、流石に山口県と感銘を受けました。明治の新政府側だけの資料だけでなく、旧幕府側からみた検証本、小説も含め、蔵書の多さに驚きます。
ただ、昨日の防府市立図書館にあった『江戸の旅人吉田松陰』(海原徹著)の本はありませんでした。高杉晋作の横井小楠と佐久間象山の批評の言葉の本はありました。地域地域で、市民の関心が異なるので、山口県内でも、蔵書に変化があると思いました。
下関市立図書館と防府市立図書館は、最新鋭の建物でしたが、山口県立図書館は、昭和の大建築家の故前川國男氏の設計で、緑の中で落ち着いて色合いの建物でした。設備等は、最新の検索機器類があり、県営の図書館の力の入れ方が違うと思いました。
せっかくと思い、地方自治、特に地方議会について分析研究をした本はないか調べましたが、熊本同様に皆無です。市民の関心は、選挙だけで議会活動には、まだまだ無関心のようです。これからは地方の時代と言われて久しいですが、市民の自治への関心力が、選挙だけではなかなか自立へ向けた動きにつながりません。
高杉晋作が、藩政の主導権を握るために、決起し行動したように、現代人は、地元自治の現場へ出向き、自分の目で確認し、意見を言い、要求をアピールする動きをやらなければ、自治改革は実現しない。特に地方議会への関心が必要と思います。
後、1時間ほど資料を調査し、ぼちぼち九州へ帰ります。
2013年08月08日
吉田松陰のロシア密航計画を支持する熊本藩士たちとの熱い交流があった。
吉田松陰のロシア密航計画を支持する熊本藩士たちとの熱い交流があった。
今日見つけた本『江戸の旅人吉田松陰』で、吉田松陰は幕末に一番日本中を歩いた旅人だったと、著者の海原徹氏が書いている。
その中で、幕末動乱前夜(1853年)に、吉田松陰がロシア艦隊に乗ろうと密航計画を企て、江戸を出たのが1853年9月10日、色々な所や人を巡りながら熊本に着いたのが10月19日夜。それからの7日間は、次々に熊本藩士と合う。
10月20日宮部鼎蔵と共に、横井小楠宅訪問、相撲町の私塾「小楠堂」を始めていた。小楠同士には、多くの実学志向の藩士が集っていた。その藩士たちが、
10月22日熊本藩士7人を訪問。
10月23日熊本藩士9人が次々来訪。
10月24日熊本藩士5人が訪ねる。
10月25日熊本藩士6人が訪ねる。
10月26日熊本の尾島(小島)港から、未明に出発した。
ところが、ロシア艦隊は松陰が長崎に着く4日前に出港していた。密航計画は頓挫した。失意に落ちて、帰路に着くが、密航を熱烈に後押しした熊本藩士に会うべく、11月5日再度、尾島港から熊本入った(帰って来た)。
11月6日に松陰の宿に、熊本藩士11人が宿を訪ねる。同日、宮部鼎蔵と熊本藩の家老有吉市兵衛を訪問。熊本藩士2人が同席。夜には、数名の来訪者があった。
11月7日熊本を出発し、柳川藩経由で、萩へ戻った。
(以上、『江戸の旅人吉田松陰』海原徹著による)
吉田松陰、宮部鼎蔵、横井小楠は、28才、38才、48才?と約10才違いに当たる。吉田松陰は、宮部鼎蔵を兄貴分として「宮部先生」と語ったいた。横井小楠は、さらに兄貴格に当たる。年代的には、佐久間象山世代になる。色々な面で影響を与えたのだと思います。
今日、下関市立図書館で、高杉晋作関連の資料を調べていて、高杉は、佐久間象山と横井小楠を「海国派」として一目をおいていた。今回の調査の主目的の一つ、禁門の変の大将格の久坂玄瑞の九州遊学の足跡調査ですが、長州を語るには、吉田松陰なしにはありえないとつくづく思いました。
維新動乱の引き金となった小競り合いの最大の事件「池田屋騒動」に深く長州と肥後(熊本)が関係していたのは、吉田松陰と宮部鼎蔵の交友が起因といて、熊本藩士と吉田松陰は深くつながっていたと思います。
明日一日、もっと史実を集めるために、山口県立図書館の郷土資料から、長州から見た幕末の熊本について、調べてみたいと思います。
今日見つけた本『江戸の旅人吉田松陰』で、吉田松陰は幕末に一番日本中を歩いた旅人だったと、著者の海原徹氏が書いている。
その中で、幕末動乱前夜(1853年)に、吉田松陰がロシア艦隊に乗ろうと密航計画を企て、江戸を出たのが1853年9月10日、色々な所や人を巡りながら熊本に着いたのが10月19日夜。それからの7日間は、次々に熊本藩士と合う。
10月20日宮部鼎蔵と共に、横井小楠宅訪問、相撲町の私塾「小楠堂」を始めていた。小楠同士には、多くの実学志向の藩士が集っていた。その藩士たちが、
10月22日熊本藩士7人を訪問。
10月23日熊本藩士9人が次々来訪。
10月24日熊本藩士5人が訪ねる。
10月25日熊本藩士6人が訪ねる。
10月26日熊本の尾島(小島)港から、未明に出発した。
ところが、ロシア艦隊は松陰が長崎に着く4日前に出港していた。密航計画は頓挫した。失意に落ちて、帰路に着くが、密航を熱烈に後押しした熊本藩士に会うべく、11月5日再度、尾島港から熊本入った(帰って来た)。
11月6日に松陰の宿に、熊本藩士11人が宿を訪ねる。同日、宮部鼎蔵と熊本藩の家老有吉市兵衛を訪問。熊本藩士2人が同席。夜には、数名の来訪者があった。
11月7日熊本を出発し、柳川藩経由で、萩へ戻った。
(以上、『江戸の旅人吉田松陰』海原徹著による)
吉田松陰、宮部鼎蔵、横井小楠は、28才、38才、48才?と約10才違いに当たる。吉田松陰は、宮部鼎蔵を兄貴分として「宮部先生」と語ったいた。横井小楠は、さらに兄貴格に当たる。年代的には、佐久間象山世代になる。色々な面で影響を与えたのだと思います。
今日、下関市立図書館で、高杉晋作関連の資料を調べていて、高杉は、佐久間象山と横井小楠を「海国派」として一目をおいていた。今回の調査の主目的の一つ、禁門の変の大将格の久坂玄瑞の九州遊学の足跡調査ですが、長州を語るには、吉田松陰なしにはありえないとつくづく思いました。
維新動乱の引き金となった小競り合いの最大の事件「池田屋騒動」に深く長州と肥後(熊本)が関係していたのは、吉田松陰と宮部鼎蔵の交友が起因といて、熊本藩士と吉田松陰は深くつながっていたと思います。
明日一日、もっと史実を集めるために、山口県立図書館の郷土資料から、長州から見た幕末の熊本について、調べてみたいと思います。
2013年08月07日
杉原千畝(ちうね)領事の決断と昼夜を費やし書き続けた6千枚のビザ
杉原千畝(ちうね)領事の決断と昼夜を費やし書き続けた6千枚のビザ
>押し寄せたユダヤ人群衆 □ 1940年(昭和15年)7月27日朝、バルト海沿岸の小国 リトアニアの日本領事館に勤務していた杉原千畝(ちうね)領事は、いつもとは違って、外 がやけに騒がしいのに気がついた。窓の外を見ると、建物の回りをびっしりと黒い人の群れが埋め尽くした。・・・・
今日のリトワニア大使と交流で話題になると思われる、第2次世界大戦前夜の東欧での民族排斥で、ユダヤ人の大量難民が出て、その人々を救った日本領事が、リトアニアにいた杉原千畝氏です。ドイツから退去命令が出るギリギリまで、ビザを書き続け、救った数は6000人を超えた。
戦前の人権の平等の考えが、領事職員に定着していたのだろうとおもいます。アメリカも、イギリスもできなかった、イスラエル難民の受け入れ、実は、上海の日本軍樋口少将も同様の行動をとり3万人近いユダヤ人を、日本経由でアメリカやイスラエルへ、逃れさせています。東洋の果ての民族日本人は、人種や出身国等で差別をしなかったのではないか。海外で仕事をした政府要人たちの中には、人権の保護を真剣に実行した人も多かったのかもしれません。
ただ、戦前の日中戦争最中のこと、イスラエル人保護とは反対に、中国への軍事進出は矛盾していると感じます。民族に上下はないと言いつつ、東アジアの中で、経済発展を最初に遂げた日本人は、他の東アジアの諸国に対して、優位な意識はないか? これから、日本人に問われる国際交流の課題と思います。
先月、熊本市で開催された「アフリカこどもの日」で、アフリカからの留学生たちが演じた劇で「平和、正義、団結」が、アフリカに必要と語っていました。これは東アジアにも通じる理念とおもます。この3つ理念を実現するには、勇気を出して、対話のテーブルに揃うことと思います。東アジアのリーダーたちに、勇気を出して対話のテーブルに着こうと呼びかけたい。
ヨーロッパの政争に翻弄されてきた歴史を持つリトアニアから、平和を維持する知恵を学ぶことは、多分にあるとおもっています。午前中の仕事を効率よく済ませ、宇土市の英語版資料を集めて、昼食会へ向かいたいと思います。
>押し寄せたユダヤ人群衆 □ 1940年(昭和15年)7月27日朝、バルト海沿岸の小国 リトアニアの日本領事館に勤務していた杉原千畝(ちうね)領事は、いつもとは違って、外 がやけに騒がしいのに気がついた。窓の外を見ると、建物の回りをびっしりと黒い人の群れが埋め尽くした。・・・・
今日のリトワニア大使と交流で話題になると思われる、第2次世界大戦前夜の東欧での民族排斥で、ユダヤ人の大量難民が出て、その人々を救った日本領事が、リトアニアにいた杉原千畝氏です。ドイツから退去命令が出るギリギリまで、ビザを書き続け、救った数は6000人を超えた。
戦前の人権の平等の考えが、領事職員に定着していたのだろうとおもいます。アメリカも、イギリスもできなかった、イスラエル難民の受け入れ、実は、上海の日本軍樋口少将も同様の行動をとり3万人近いユダヤ人を、日本経由でアメリカやイスラエルへ、逃れさせています。東洋の果ての民族日本人は、人種や出身国等で差別をしなかったのではないか。海外で仕事をした政府要人たちの中には、人権の保護を真剣に実行した人も多かったのかもしれません。
ただ、戦前の日中戦争最中のこと、イスラエル人保護とは反対に、中国への軍事進出は矛盾していると感じます。民族に上下はないと言いつつ、東アジアの中で、経済発展を最初に遂げた日本人は、他の東アジアの諸国に対して、優位な意識はないか? これから、日本人に問われる国際交流の課題と思います。
先月、熊本市で開催された「アフリカこどもの日」で、アフリカからの留学生たちが演じた劇で「平和、正義、団結」が、アフリカに必要と語っていました。これは東アジアにも通じる理念とおもます。この3つ理念を実現するには、勇気を出して、対話のテーブルに揃うことと思います。東アジアのリーダーたちに、勇気を出して対話のテーブルに着こうと呼びかけたい。
ヨーロッパの政争に翻弄されてきた歴史を持つリトアニアから、平和を維持する知恵を学ぶことは、多分にあるとおもっています。午前中の仕事を効率よく済ませ、宇土市の英語版資料を集めて、昼食会へ向かいたいと思います。
2013年08月04日
〈異業種交流会〉出会いが起点となるには、常に積極的でなければならない。
〈異業種交流会〉出会いが起点となるには、常に積極的でなければならない。
さて、異業種交流会を始めるきっかけは、消費税アップが原因だった。消費税が3%から5%に上がる時、日本は空前の建築ブームで、私のような田舎の建築士でも、寝る間を惜しむような忙しさだった。仕事を間に合わせるために、手伝ってくれる設計士を捜し、どうにか間に合わせることが出来た。
ところが、工事が始まると図面の食い違いに、現場で大いに苦労した。そのころ友人が、仲間作りの話を持ちかけて来た。半年間、二人で夜な夜な何度も酒を飲みながら、語り合った。後半は、もう二人を加え月に1回集まり、意見を交わしたが、なかなか進まない。
結局、翌年(1997年)に、当初の二人が友人知人に、九州の巨大プロジェクトの見学会を呼びかけ、ワゴン車2台で15人が、大分のコンベンションセンターの見学を皮切りに、鹿児島、福岡、下関のプロジェクトを見学し、1度研修会を私の事務所で開催した。
その年末に、もう15人を加えて忘年会を開催した。それが好評で、翌年に居酒屋談義を44名でやり、工期短縮プロジェクトや国内の設計コンペに挑戦したりしながら、秋に55名の交流会を開催した。
今のような、ホテル等で「講演+交流」のスタイルは、3年目に定着して以来続けて来て、前週末の「夏の会」で53回目の集まりになった。当初から来ている人は減ったが、現在のスタイルなって15年目ですが、常に新しい方をお誘いし、新たな出会いの機会と、講師とのつながりを作ることを目的に続けて来ました。
毎回講師は、その時々の出会いや、長く縁のある方、講師からの紹介等から選択しますので、参加する方も興味る方の時に参加するゆるさが、継続きたのではと考えます。年会費無し、毎回清算で、来た人は必ず新しい出会いがある。不透明な仕事の方は、ご案内をしていません。
私の会がご縁で、会社設立の協力スタッフが見つかったり、大学講師に引っ張りだされたり、合同会社を作ったり、色々な出会いが起きました。私自身も、毎回刺激を受けています。私が、勝手に集める異業種交流会が、何でここまで続けて来れたかは、友人たちの協力のおかげです。
現在の企業(仕事)は、一社で全てを完結できる時代は終わりました。良きパートナーとタッグを組み、高い完成度を達成するには、グローバル企業だけでなく、地方の自営業者も地域の志ある人材と連携し、困難な仕事にチャレンジすることが必要と思います。
昨日の二日市の店舗オーナーは、論語・易経、等の人生の指針を学ぶ師でもあるのですが、先生から「野口さんは、仕事(目先利益)を追わなかったから続いている」と話されました。私は、人への興味から色々な方と会ってきました。人の紹介、新聞記事、あるいは講演会の講師、等々。ボランティア活動にも参加し、若い市民リーダーとの出会いは、私自身の考えを変えて来たと思います。
これからも細々と続ける異業種交流会『四季の会』ですが、社会を支える独立独歩のリーダーに関心のある方は、時間と興味があるとき、春夏秋冬に開催する集いに、ご参加いただければ幸いです。
私の貧相な人生経験から「人生は出会いで決まる。その出会いは、遅くもなく早くもなく起こる。出会いが起点となるには、常に積極的でなければならない」と考えています。色々ご意見をいただければありがたいです。最後に、休日の長文を最後までお読みいただき感謝します。
さて、異業種交流会を始めるきっかけは、消費税アップが原因だった。消費税が3%から5%に上がる時、日本は空前の建築ブームで、私のような田舎の建築士でも、寝る間を惜しむような忙しさだった。仕事を間に合わせるために、手伝ってくれる設計士を捜し、どうにか間に合わせることが出来た。
ところが、工事が始まると図面の食い違いに、現場で大いに苦労した。そのころ友人が、仲間作りの話を持ちかけて来た。半年間、二人で夜な夜な何度も酒を飲みながら、語り合った。後半は、もう二人を加え月に1回集まり、意見を交わしたが、なかなか進まない。
結局、翌年(1997年)に、当初の二人が友人知人に、九州の巨大プロジェクトの見学会を呼びかけ、ワゴン車2台で15人が、大分のコンベンションセンターの見学を皮切りに、鹿児島、福岡、下関のプロジェクトを見学し、1度研修会を私の事務所で開催した。
その年末に、もう15人を加えて忘年会を開催した。それが好評で、翌年に居酒屋談義を44名でやり、工期短縮プロジェクトや国内の設計コンペに挑戦したりしながら、秋に55名の交流会を開催した。
今のような、ホテル等で「講演+交流」のスタイルは、3年目に定着して以来続けて来て、前週末の「夏の会」で53回目の集まりになった。当初から来ている人は減ったが、現在のスタイルなって15年目ですが、常に新しい方をお誘いし、新たな出会いの機会と、講師とのつながりを作ることを目的に続けて来ました。
毎回講師は、その時々の出会いや、長く縁のある方、講師からの紹介等から選択しますので、参加する方も興味る方の時に参加するゆるさが、継続きたのではと考えます。年会費無し、毎回清算で、来た人は必ず新しい出会いがある。不透明な仕事の方は、ご案内をしていません。
私の会がご縁で、会社設立の協力スタッフが見つかったり、大学講師に引っ張りだされたり、合同会社を作ったり、色々な出会いが起きました。私自身も、毎回刺激を受けています。私が、勝手に集める異業種交流会が、何でここまで続けて来れたかは、友人たちの協力のおかげです。
現在の企業(仕事)は、一社で全てを完結できる時代は終わりました。良きパートナーとタッグを組み、高い完成度を達成するには、グローバル企業だけでなく、地方の自営業者も地域の志ある人材と連携し、困難な仕事にチャレンジすることが必要と思います。
昨日の二日市の店舗オーナーは、論語・易経、等の人生の指針を学ぶ師でもあるのですが、先生から「野口さんは、仕事(目先利益)を追わなかったから続いている」と話されました。私は、人への興味から色々な方と会ってきました。人の紹介、新聞記事、あるいは講演会の講師、等々。ボランティア活動にも参加し、若い市民リーダーとの出会いは、私自身の考えを変えて来たと思います。
これからも細々と続ける異業種交流会『四季の会』ですが、社会を支える独立独歩のリーダーに関心のある方は、時間と興味があるとき、春夏秋冬に開催する集いに、ご参加いただければ幸いです。
私の貧相な人生経験から「人生は出会いで決まる。その出会いは、遅くもなく早くもなく起こる。出会いが起点となるには、常に積極的でなければならない」と考えています。色々ご意見をいただければありがたいです。最後に、休日の長文を最後までお読みいただき感謝します。
2013年08月02日
自分の長所・短所をしっかりと見据えて志を立てる
自分の長所・短所をしっかりと見据えて志を立てる
おはようございます。少し早めに目が覚めました。
今夜は異業種交流会ですが、午前中に準備をして、午後は昨日打ち合わせた住宅の模型作りを始めます。模型は日常の仕事をしながらなので、製作に1週間近くかかります。でも、模型で確認をしておくと、ほとんど間違いがない。現場では、やり直しが一番大変んなので、最初に時間をかけた方が、工事はスムーズに行くように思います。
さて建築工事で模型に時間を要するように、人生の歩みも当初に時間をかけ、自分を分析し、強み・弱点、周りの環境、時代変化、等々を緻密に分析を行ってから、進む道を選択することが必要と思います。
明治の経済人をリードした渋沢栄一は、「世の流行に流される人は多い。周囲の声に左右され、自分の心にもない方向へ進んでしまう人もいる」と。貴重な時間を使いながらも、それでは自分を見失うだけで、成功には至らない。渋沢栄一は、自分の能力、環境の分析について、こう語っている。
「まず冷静になり、自分の長所と短所を考察する。長所を伸ばせるところに志を定める。同時に、環境がその志を許すかも考える必要がある。頭が良くても、実家に財力がなければ難しい。よって、一生やり通す見込みが出来て、志を確立する」
時流に流されず、自分のやりたいこと、自分の行きたい道をしっかりと見据えなければ、志を立てたとはいえない。明治の偉人の言葉は、明治維新を乗り越えた苦労から来るので、厳しいが現代にも充分通用する訓示と思います。
朝から硬い話になりましたが、外が白んできました。そろそろ、準備して早朝ウォーキングに出かけます。明日で、朝ウォーキングも丸1年になります。
おはようございます。少し早めに目が覚めました。
今夜は異業種交流会ですが、午前中に準備をして、午後は昨日打ち合わせた住宅の模型作りを始めます。模型は日常の仕事をしながらなので、製作に1週間近くかかります。でも、模型で確認をしておくと、ほとんど間違いがない。現場では、やり直しが一番大変んなので、最初に時間をかけた方が、工事はスムーズに行くように思います。
さて建築工事で模型に時間を要するように、人生の歩みも当初に時間をかけ、自分を分析し、強み・弱点、周りの環境、時代変化、等々を緻密に分析を行ってから、進む道を選択することが必要と思います。
明治の経済人をリードした渋沢栄一は、「世の流行に流される人は多い。周囲の声に左右され、自分の心にもない方向へ進んでしまう人もいる」と。貴重な時間を使いながらも、それでは自分を見失うだけで、成功には至らない。渋沢栄一は、自分の能力、環境の分析について、こう語っている。
「まず冷静になり、自分の長所と短所を考察する。長所を伸ばせるところに志を定める。同時に、環境がその志を許すかも考える必要がある。頭が良くても、実家に財力がなければ難しい。よって、一生やり通す見込みが出来て、志を確立する」
時流に流されず、自分のやりたいこと、自分の行きたい道をしっかりと見据えなければ、志を立てたとはいえない。明治の偉人の言葉は、明治維新を乗り越えた苦労から来るので、厳しいが現代にも充分通用する訓示と思います。
朝から硬い話になりましたが、外が白んできました。そろそろ、準備して早朝ウォーキングに出かけます。明日で、朝ウォーキングも丸1年になります。
2013年08月01日
異業種交流会「夏の会」は、当日参加も加えて30名になりそうです。
異業種交流会「夏の会」は、当日参加も加えて30名になりそうです。
久々の異業種交流会で、冬と春を休みましたので、葯半年ぶりの集いです。たいへん多い参集に、感謝申し上げます。
今回は、Facebookの仲間を中心に呼びかけました。テーマが、日本の戦後政治から現代の政治情勢まで、硬い話題で、集まるか心配でしたが、30名近い参加は嬉しい結果になりそうです。まったく新しい方が、約半分近いですが、facebookでつながりができて方ばかりですので、全くの初めてではないですが、リアルな出会いにつながると思います。
鈴木教授の今度の講義の一部に、時代背景に子供おもちゃである「リカちゃん人形」の成長と日本家庭、企業戦士との関係、政治がどんな政策で、生活を支えて来たか、リカちゃん人形の発展と日本社会、面白い視点と思います。
多分、今回は参議院選挙後の話題も出てくるので、私の聞いた講義とはだいぶちがったものになるはずです。関心のある方で、1時間ならどうにかできる人は、会場へ足をお運びください。話のネタになることが、必ずあると思います。53回目の異業種交流会、どんなことが起こるか、私自身がとても楽しみです。
会場にこれない方は、後日、私の公式ブログ
http://noguchi-shuichi.at.webry.info/
または、環境共生施設研究所のブログ
http://aandekyouseiken.otemo-yan.net/
を検索してください。講演内容を整理して掲載いたします。
ちなみに、私の公式ブログが、初めて1月のアクセスが9000をオーバーしました。昨年までは、1月の平均が7000前後、今年前半なり7500前後、夏になり8000近くを推移し、夏の暑さからか、7月は9227アクセスでした。8月も行事が多いので、話題豊富かと思っています。Facebookと内容は似ていますが、行事の写真が夏は増えるので、時々検索すると私の写った写真も見れます。日ごろどんなことをやっているか、検索いただければ幸いです。
久々の異業種交流会で、冬と春を休みましたので、葯半年ぶりの集いです。たいへん多い参集に、感謝申し上げます。
今回は、Facebookの仲間を中心に呼びかけました。テーマが、日本の戦後政治から現代の政治情勢まで、硬い話題で、集まるか心配でしたが、30名近い参加は嬉しい結果になりそうです。まったく新しい方が、約半分近いですが、facebookでつながりができて方ばかりですので、全くの初めてではないですが、リアルな出会いにつながると思います。
鈴木教授の今度の講義の一部に、時代背景に子供おもちゃである「リカちゃん人形」の成長と日本家庭、企業戦士との関係、政治がどんな政策で、生活を支えて来たか、リカちゃん人形の発展と日本社会、面白い視点と思います。
多分、今回は参議院選挙後の話題も出てくるので、私の聞いた講義とはだいぶちがったものになるはずです。関心のある方で、1時間ならどうにかできる人は、会場へ足をお運びください。話のネタになることが、必ずあると思います。53回目の異業種交流会、どんなことが起こるか、私自身がとても楽しみです。
会場にこれない方は、後日、私の公式ブログ
http://noguchi-shuichi.at.webry.info/
または、環境共生施設研究所のブログ
http://aandekyouseiken.otemo-yan.net/
を検索してください。講演内容を整理して掲載いたします。
ちなみに、私の公式ブログが、初めて1月のアクセスが9000をオーバーしました。昨年までは、1月の平均が7000前後、今年前半なり7500前後、夏になり8000近くを推移し、夏の暑さからか、7月は9227アクセスでした。8月も行事が多いので、話題豊富かと思っています。Facebookと内容は似ていますが、行事の写真が夏は増えるので、時々検索すると私の写った写真も見れます。日ごろどんなことをやっているか、検索いただければ幸いです。
2013年08月01日
大陸の辺境民族の日本だったから異文化を飲み込み、変化させ成長を続けてきた
大陸の辺境民族の日本だったから異文化を飲み込み、変化させ成長を続けてきた
おはようございます。今日は、真夏の朝の風景です。
さて、東京の夜の会食後に、数名で2次会へ出た。スナックでの会話の中で、客の相手をしてくれたのは、長崎、北海道、群馬、北陸地方の若い女性たち、「夢を追って東京へ出て来た」と語っていた。昼は、昼で仕事をして、「週に2〜4日アルバイトし、次のステップのため少しでも準備資金になるように働いている」と。
先輩議員と帰りのタクシーの中で、「都会は、今も昔も地方の若者が支えている」と、日本国内を見ても都会に夢を追って、地方から人材が集まる。『バカと笑われるリーダーが最後に勝つ』の一節に、昭和の日本を代表する知識人の言葉があった。
文化人類学者の故梅棹忠夫氏の『文明の生態史』の一文が紹介されていた。
「(日本人は)本当の文化は、どこかほかのところで作られるものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識である。おそらくこれは、はじめから自分自身を中心にしてひとつの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境民族のひとつとしてスタートした民族とのちがいがあろうとおもう」
また、昭和を代表する政治学者で思想史家の故丸山真男氏の『日本の思想』の一文が紹介され、なるほどと思った。
「新たなもの、本来異質的なものまでが過去との十分な対決なしにつぎつぎと摂取されるから、新たなものの勝利は驚くほど早い。過去は過去として自覚的に現在と向き合わずに、傍におしやられ、あるいは下に沈降して意識から消え『忘却』される」
日本の新し物好きは、「ナショナル・アムネジアー国民的健忘症」という特性と深く関わっている、とあった。いつも新しいことに飛びつく。変化に着いて行く順能力は、世界有数の人類と思います。
今日は、900年近い歴史を持つ、地元の神社の夏の祭りが開催される。各家々の人の名前を、裃の形に切り抜いた白紙に書き、神社に備え無病息災を願う。古き伝統だが、若い世代は誰も来ない。文化を「こだわり」と表現する人がいます。
文明は、人類に共通する便利な生活を作り出す。古代では仏教と稲作が中国大陸から入って来た。遣唐使、遣隋使として若者が大陸へ渡った。明治では蒸気船、鉄道、電信、等々、西洋文明の新しい技術が入って来た。多くの若者が、ヨーロッパ、アメリカへ渡った。今、世界の大都市となった東京へ、日本だけでなく、アジア、世界から若者たちが集まる。
日本人は、常に新しいものを求め、真似し、自分のスタイルにし、最後には「メイド ・イン ・ジャパン」にして、国内や国外へ送り出す。中国を発祥とする論語は、朱子学、陽明学生み出し、日本文化に影響を与えた。明治維新を動かした志士たちの多くが陽明学を学んでいたと言われている。
日本の国民的健忘症は、これからも続くと思うが、そろそろ日本人が積み上げて来た文化を、検証する機運が起きて欲しい。加えて、大陸から見れば、辺境民族の日本だが、世界の文明・文化を取り込み、さらにより良き文明として送り出し、世界に影響を与える民族になることを願います。
おはようございます。今日は、真夏の朝の風景です。
さて、東京の夜の会食後に、数名で2次会へ出た。スナックでの会話の中で、客の相手をしてくれたのは、長崎、北海道、群馬、北陸地方の若い女性たち、「夢を追って東京へ出て来た」と語っていた。昼は、昼で仕事をして、「週に2〜4日アルバイトし、次のステップのため少しでも準備資金になるように働いている」と。
先輩議員と帰りのタクシーの中で、「都会は、今も昔も地方の若者が支えている」と、日本国内を見ても都会に夢を追って、地方から人材が集まる。『バカと笑われるリーダーが最後に勝つ』の一節に、昭和の日本を代表する知識人の言葉があった。
文化人類学者の故梅棹忠夫氏の『文明の生態史』の一文が紹介されていた。
「(日本人は)本当の文化は、どこかほかのところで作られるものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識である。おそらくこれは、はじめから自分自身を中心にしてひとつの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境民族のひとつとしてスタートした民族とのちがいがあろうとおもう」
また、昭和を代表する政治学者で思想史家の故丸山真男氏の『日本の思想』の一文が紹介され、なるほどと思った。
「新たなもの、本来異質的なものまでが過去との十分な対決なしにつぎつぎと摂取されるから、新たなものの勝利は驚くほど早い。過去は過去として自覚的に現在と向き合わずに、傍におしやられ、あるいは下に沈降して意識から消え『忘却』される」
日本の新し物好きは、「ナショナル・アムネジアー国民的健忘症」という特性と深く関わっている、とあった。いつも新しいことに飛びつく。変化に着いて行く順能力は、世界有数の人類と思います。
今日は、900年近い歴史を持つ、地元の神社の夏の祭りが開催される。各家々の人の名前を、裃の形に切り抜いた白紙に書き、神社に備え無病息災を願う。古き伝統だが、若い世代は誰も来ない。文化を「こだわり」と表現する人がいます。
文明は、人類に共通する便利な生活を作り出す。古代では仏教と稲作が中国大陸から入って来た。遣唐使、遣隋使として若者が大陸へ渡った。明治では蒸気船、鉄道、電信、等々、西洋文明の新しい技術が入って来た。多くの若者が、ヨーロッパ、アメリカへ渡った。今、世界の大都市となった東京へ、日本だけでなく、アジア、世界から若者たちが集まる。
日本人は、常に新しいものを求め、真似し、自分のスタイルにし、最後には「メイド ・イン ・ジャパン」にして、国内や国外へ送り出す。中国を発祥とする論語は、朱子学、陽明学生み出し、日本文化に影響を与えた。明治維新を動かした志士たちの多くが陽明学を学んでいたと言われている。
日本の国民的健忘症は、これからも続くと思うが、そろそろ日本人が積み上げて来た文化を、検証する機運が起きて欲しい。加えて、大陸から見れば、辺境民族の日本だが、世界の文明・文化を取り込み、さらにより良き文明として送り出し、世界に影響を与える民族になることを願います。