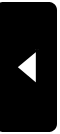2007年09月11日
幸も不幸も心の持ち方次第」
幸も不幸も心の持ち方次第
幸福も不幸も、すべて心の持ち方から生まれてくる。
釈迦も、「欲望が燃えさかれば、この世は焦熱地獄。貧欲におちこめば、人生は苦しみの海。心さえ清らかになれば、燃えさかる炎も涼しげな池となり、迷いからさめさえすれば、解脱の境地に達する」と語っている。
心の持ち方を少し変えただけで、この世のなかはがらりと変える。くれぐれも慎重に対処したい。
「足る知れば辱められず、止めを知ればあやうからず」
上記は、老子の教えですが、「おれがおれが」と出しゃばる態度、自分の利益追求のためには、他人の迷惑もおかまいなしの生き方を戒めている。
足るを知らず、止まるを知らずに生きていれば、周囲の反感を買い、いずれ袋叩きに遭うのがオチだ、と訓示います。
幸福も不幸も、すべて心の持ち方から生まれてくる。
釈迦も、「欲望が燃えさかれば、この世は焦熱地獄。貧欲におちこめば、人生は苦しみの海。心さえ清らかになれば、燃えさかる炎も涼しげな池となり、迷いからさめさえすれば、解脱の境地に達する」と語っている。
心の持ち方を少し変えただけで、この世のなかはがらりと変える。くれぐれも慎重に対処したい。
「足る知れば辱められず、止めを知ればあやうからず」
上記は、老子の教えですが、「おれがおれが」と出しゃばる態度、自分の利益追求のためには、他人の迷惑もおかまいなしの生き方を戒めている。
足るを知らず、止まるを知らずに生きていれば、周囲の反感を買い、いずれ袋叩きに遭うのがオチだ、と訓示います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
20:43
│Comments(0)
2007年09月11日
曹子曰く、吾日に吾が身を三省す
曹子曰く、吾日に吾が身を三省す
(意味)
(曹先生が言われた)、私は毎日、自分をたびたびかえりみて、良くないことをはぶいている。人の為を思うて、真心からやったかどうか。友達と交わってうそいつわりはなかったか。まだ習得していないことを人に教えるようなことはなかったか。
一日三省の言葉は、ここから出てたと言われています。また出版社の「三省堂」の語源と聞きました。時間を見つけて、自分を省みるゆとりを持ちたいものです。
(意味)
(曹先生が言われた)、私は毎日、自分をたびたびかえりみて、良くないことをはぶいている。人の為を思うて、真心からやったかどうか。友達と交わってうそいつわりはなかったか。まだ習得していないことを人に教えるようなことはなかったか。
一日三省の言葉は、ここから出てたと言われています。また出版社の「三省堂」の語源と聞きました。時間を見つけて、自分を省みるゆとりを持ちたいものです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
20:40
│Comments(0)
2007年09月11日
学べば独善、頑固でなくなる
学べば独善、頑固でなくなる
「子曰く、君子、重からざれば則(すなわ)」ち威あらず。学べば則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。過てば則ち改むるに憚(はばか)ることなかれ。」
(解説)
孔子先生が言われた、「上に立つ人は、言動を重々しくしないと威厳がなくなる。学べば独善、頑固でなくなる。忠信を第一とし、安易に自分より知徳の劣った者と交わっていい気になってはならない。そして過ちに気づいたら改めるのに誰にも遠慮はいらない。」
(感想)
最近人の話を聞くこと、語ることが多いのですが、言葉ひとつひとつがどう影響するか受けてのことも考えつつ、急がずに話しことに気を付けるようになりました。威厳を保つためでなく、独善にならないように、まず人の話をよく聞くことが大事なように感じています。
「子曰く、君子、重からざれば則(すなわ)」ち威あらず。学べば則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。過てば則ち改むるに憚(はばか)ることなかれ。」
(解説)
孔子先生が言われた、「上に立つ人は、言動を重々しくしないと威厳がなくなる。学べば独善、頑固でなくなる。忠信を第一とし、安易に自分より知徳の劣った者と交わっていい気になってはならない。そして過ちに気づいたら改めるのに誰にも遠慮はいらない。」
(感想)
最近人の話を聞くこと、語ることが多いのですが、言葉ひとつひとつがどう影響するか受けてのことも考えつつ、急がずに話しことに気を付けるようになりました。威厳を保つためでなく、独善にならないように、まず人の話をよく聞くことが大事なように感じています。
Posted by ノグチ(noguchi) at
06:52
│Comments(0)
2007年09月11日
誰にも譲れない一線がある
誰にも譲れない一線がある
今日のテレビで、安倍首相が「仕事を賭して、法案成立に臨む」と記者会見が有りました。「排水の陣」の気迫を感じるニュースでした。やはり、緊張無き論戦は迫力を欠くので、野党も気持ちを引き締めて、論破するくらいの気持ちが必要と思うし、保守側も本来の国会の場で、国民に指示を得られるような、譲れない理念を掲げて世に訴えて欲しい意図願います。
さて、譲れない理念をよく「誰にも譲れない一線」があると言葉に出しますが、人それぞれに譲れない思いこそが、一線=分岐点を示していると思います。こだわりとも言いますが、そのこだわりに賛同する支援者がでてきて、当事者も益々こだわり続けることが可能になります。
ある本で、東京のおいしいそば屋がこだわり、良いそば粉を求めて山梨の田舎に引っ越した。でも、そのそば屋のそばを食べたくて、東京からやって来る客もいるとか。徹底して自分の信念を貫き通せば、ちゃんと 認めてくれる人がいる。
その信念について、孟子の弟子が師に聞きました。すると、
「自分の持っている原理、原則に曲げて相手に迎合する人物に、立派な指導者はいない。」
また、孟子の訓示が次の言葉です。
「已むべからざるに於いて已むる者は、已まざる所なし。」
いくら凡ミスを重ねて来ていても、強いチームは正念場になると目の色が変わり、凄まじいばかりの集中力を発揮する。
世には、ここぞという時に、踏ん張る人間と踏ん張れずに、挫折してしまう人間とがいる。これは、人生もいえるのではないか。
そのひと山を乗り越えれば、大きく展望が開け、更には人間の器をひと廻り大きくできる。
*参考資料:守屋洋著「中国古典」
最後に、良寛の教示。
「欲望の少ない人で良心のない人はわずかである。」
みなさんのこだわり発言を楽しみにしていました。
今日のテレビで、安倍首相が「仕事を賭して、法案成立に臨む」と記者会見が有りました。「排水の陣」の気迫を感じるニュースでした。やはり、緊張無き論戦は迫力を欠くので、野党も気持ちを引き締めて、論破するくらいの気持ちが必要と思うし、保守側も本来の国会の場で、国民に指示を得られるような、譲れない理念を掲げて世に訴えて欲しい意図願います。
さて、譲れない理念をよく「誰にも譲れない一線」があると言葉に出しますが、人それぞれに譲れない思いこそが、一線=分岐点を示していると思います。こだわりとも言いますが、そのこだわりに賛同する支援者がでてきて、当事者も益々こだわり続けることが可能になります。
ある本で、東京のおいしいそば屋がこだわり、良いそば粉を求めて山梨の田舎に引っ越した。でも、そのそば屋のそばを食べたくて、東京からやって来る客もいるとか。徹底して自分の信念を貫き通せば、ちゃんと 認めてくれる人がいる。
その信念について、孟子の弟子が師に聞きました。すると、
「自分の持っている原理、原則に曲げて相手に迎合する人物に、立派な指導者はいない。」
また、孟子の訓示が次の言葉です。
「已むべからざるに於いて已むる者は、已まざる所なし。」
いくら凡ミスを重ねて来ていても、強いチームは正念場になると目の色が変わり、凄まじいばかりの集中力を発揮する。
世には、ここぞという時に、踏ん張る人間と踏ん張れずに、挫折してしまう人間とがいる。これは、人生もいえるのではないか。
そのひと山を乗り越えれば、大きく展望が開け、更には人間の器をひと廻り大きくできる。
*参考資料:守屋洋著「中国古典」
最後に、良寛の教示。
「欲望の少ない人で良心のない人はわずかである。」
みなさんのこだわり発言を楽しみにしていました。
Posted by ノグチ(noguchi) at
00:18
│Comments(0)
2007年09月10日
人から受けた恩は忘れるな
人から受けた恩は忘れるな(菜根譚より)
人の施した恩恵は忘れてしまったほうがよい。だが、人にかけた迷惑は忘れてはならない。人から受けた恩義は忘れてはならない。だが、人から受けた怨みは忘れてしまったほうがよい。
(解説)
人間は独りでは生きられない。だれでも生まれてからこのかた、親の恩に始まって、多くの人の恩を受けて今日がある。その恩にどう報いればよいのか。
一言でいえば、「人から受けた恩は忘れるな。人の与えた恩は忘れてしまえ。」だという。受けた恩は忘れないで憶えておいて、お返しできるようになったら、お返しすればよいのである。これもまた基本的な人生の作法の一つと言ってよい。
人の施した恩恵は忘れてしまったほうがよい。だが、人にかけた迷惑は忘れてはならない。人から受けた恩義は忘れてはならない。だが、人から受けた怨みは忘れてしまったほうがよい。
(解説)
人間は独りでは生きられない。だれでも生まれてからこのかた、親の恩に始まって、多くの人の恩を受けて今日がある。その恩にどう報いればよいのか。
一言でいえば、「人から受けた恩は忘れるな。人の与えた恩は忘れてしまえ。」だという。受けた恩は忘れないで憶えておいて、お返しできるようになったら、お返しすればよいのである。これもまた基本的な人生の作法の一つと言ってよい。
Posted by ノグチ(noguchi) at
23:43
│Comments(0)
2007年09月10日
正しい人を用いれば、民は心から服す
正しい人を用いれば、民は心から服す
「哀公問うて曰く、何を為さば則(すなわ)ち民服せん。」
「孔子答えて曰わく、直きを挙げて諸(これ)を、まがれる(王)におけば則ち民服す。」
(解説)
哀公(魯の君主)が、孔子先生に尋ねた「どうすれば民は心から服するか?」
孔子先生は答えた「正しい人を挙げ用いて、まがった人の上におけば、民は心から服す。まがった人を挙げ用いて、正しい人の上におけば、民は心から服しません。」
(感想)
これって、現代に十分通用する教示と感じます。日本の前内閣や、最近の官製談合自治体、官僚の贈収賄事件に関わる人には、耳に痛い言葉と思います。2500年の時を越えて、孔子の教えのすばらしさを感じます。
これは政治だけでなく、色々な組織にも言えることだと思います。政治と言う言葉を聞くと、硬いイメージがありますが、
「政治とは?=市民の思い(参加者の思い、組織人の思い)」
と思います。色々な集まり、会合、さらには組織、団体、会社、あるいはボランティア・グループ、福祉団体を含め、集団では参加する一人ひとりの思いを組み上げ、全体でどう動くか考え決断し、行動に写す時に、下す人事と判断で、政治(支持)の良し悪しが出ます。
大きな組織であれ、家族であれ、参加する思いを汲み取り、より良い方向へ導くのがリーダーと思います。誰をトップに据えるかで、組織の意識が大きく変ることが多々あります。そして、組織に誰を入れるかは、トップの裁量ですが、ここも重要と思います。
民意を汲み取るには何が必要か、常に変化する思い(政治)に注意を払う続けることが必要と思います。
みなさんの団体のリーダーはいかがでしょうか?私自身も常に問われていると思います。反省と決断を常に緊張して考えることと思っています。
「哀公問うて曰く、何を為さば則(すなわ)ち民服せん。」
「孔子答えて曰わく、直きを挙げて諸(これ)を、まがれる(王)におけば則ち民服す。」
(解説)
哀公(魯の君主)が、孔子先生に尋ねた「どうすれば民は心から服するか?」
孔子先生は答えた「正しい人を挙げ用いて、まがった人の上におけば、民は心から服す。まがった人を挙げ用いて、正しい人の上におけば、民は心から服しません。」
(感想)
これって、現代に十分通用する教示と感じます。日本の前内閣や、最近の官製談合自治体、官僚の贈収賄事件に関わる人には、耳に痛い言葉と思います。2500年の時を越えて、孔子の教えのすばらしさを感じます。
これは政治だけでなく、色々な組織にも言えることだと思います。政治と言う言葉を聞くと、硬いイメージがありますが、
「政治とは?=市民の思い(参加者の思い、組織人の思い)」
と思います。色々な集まり、会合、さらには組織、団体、会社、あるいはボランティア・グループ、福祉団体を含め、集団では参加する一人ひとりの思いを組み上げ、全体でどう動くか考え決断し、行動に写す時に、下す人事と判断で、政治(支持)の良し悪しが出ます。
大きな組織であれ、家族であれ、参加する思いを汲み取り、より良い方向へ導くのがリーダーと思います。誰をトップに据えるかで、組織の意識が大きく変ることが多々あります。そして、組織に誰を入れるかは、トップの裁量ですが、ここも重要と思います。
民意を汲み取るには何が必要か、常に変化する思い(政治)に注意を払う続けることが必要と思います。
みなさんの団体のリーダーはいかがでしょうか?私自身も常に問われていると思います。反省と決断を常に緊張して考えることと思っています。
Posted by ノグチ(noguchi) at
22:15
│Comments(0)
2007年09月10日
「人望」の求心力:桃李不言下自成蹊(史記より)
「人望」の求心力:桃李不言下自成蹊(史記より)
~桃李(とうり)もの言わずして、下自ずから蹊(みち)を成す~
司馬遷と言う中国の歴史家が書いたと言われる「史記」のことを解説した本(中国古典一日一話:守屋洋著)に、次の言葉がありました。
「桃李不言下自成蹊」
「桃李(とうり)もの言わずして、下自ずから蹊(みち)を成す」
この一節から、東京の成蹊大学の名が取られたとも書かれていました。守屋氏の解説を読むと、
(本文、転載)
漢の時代に、李広という将軍が居た、「漢の飛将軍」と怖れれた豪胆な軍人だったが、普段は無口で朴訥な人柄だった。
私欲の無い人で、恩賞の類はことごとく部下に分けてやった。食料も、部下に行き渡るまで先に口につけることがなかったし、行軍中に泉に辿りついても、部下が飲み終わるまで、決して飲もうとしなかったという。そのために李広の部下は全員、彼のために死を厭わぬ決意で戦いに臨んだという。
初めの言葉は、その李広を評したものです。桃や李の樹は、何も言わないが、美しい花を咲かせ、果実を実らせる。だから、自然に人々が集まって来て道ができる。つまり、徳のある人物の下には、黙っていても人が慕って寄ってくるということだ。・・・
(中国古典一日一話:守屋洋著)
西郷隆盛を評した人が、「西郷さんは、磁石のような人、遭う度に益々好きになって行く」と語った文を読んだことがあります。
反対に、いくら能力が有っても、人望のない人間にはリーダーの資格がない。人望がなかったら、まわりに人が集まってこなくなり、そうなると必要な情報も入って来なくなる。
高い企画能力、事業力も大事ですが、人間としての魅力が無いと仲間集め(集まる)が継続できないと感じます。人を惹きつける魅力とは、何千年も昔からの課題ですが、自分の周りに居る人たちを見ると、好意を持つ人、違和感を感じる人の両方がいます。「人望」とは、その人が何かする時に「手伝ったあげたい」と思う気持ちと思います。
知識、理論で形を整える能力・実績(ハードパワー)も大事ですが、人を惹きつける魅力(ソフトパワー)も忘れないことと思います。
人間は、一人ひとりが違う文化(価値)を持っています。違った文化を持つ人間が、ぶつかっても、受け入れる心の容量の大きさが人望と考えます。
そのような地域の先輩を目標して、日々私も自分を高めることに気を付けながら、人との交流を大事にして行きたいと思っています。
~桃李(とうり)もの言わずして、下自ずから蹊(みち)を成す~
司馬遷と言う中国の歴史家が書いたと言われる「史記」のことを解説した本(中国古典一日一話:守屋洋著)に、次の言葉がありました。
「桃李不言下自成蹊」
「桃李(とうり)もの言わずして、下自ずから蹊(みち)を成す」
この一節から、東京の成蹊大学の名が取られたとも書かれていました。守屋氏の解説を読むと、
(本文、転載)
漢の時代に、李広という将軍が居た、「漢の飛将軍」と怖れれた豪胆な軍人だったが、普段は無口で朴訥な人柄だった。
私欲の無い人で、恩賞の類はことごとく部下に分けてやった。食料も、部下に行き渡るまで先に口につけることがなかったし、行軍中に泉に辿りついても、部下が飲み終わるまで、決して飲もうとしなかったという。そのために李広の部下は全員、彼のために死を厭わぬ決意で戦いに臨んだという。
初めの言葉は、その李広を評したものです。桃や李の樹は、何も言わないが、美しい花を咲かせ、果実を実らせる。だから、自然に人々が集まって来て道ができる。つまり、徳のある人物の下には、黙っていても人が慕って寄ってくるということだ。・・・
(中国古典一日一話:守屋洋著)
西郷隆盛を評した人が、「西郷さんは、磁石のような人、遭う度に益々好きになって行く」と語った文を読んだことがあります。
反対に、いくら能力が有っても、人望のない人間にはリーダーの資格がない。人望がなかったら、まわりに人が集まってこなくなり、そうなると必要な情報も入って来なくなる。
高い企画能力、事業力も大事ですが、人間としての魅力が無いと仲間集め(集まる)が継続できないと感じます。人を惹きつける魅力とは、何千年も昔からの課題ですが、自分の周りに居る人たちを見ると、好意を持つ人、違和感を感じる人の両方がいます。「人望」とは、その人が何かする時に「手伝ったあげたい」と思う気持ちと思います。
知識、理論で形を整える能力・実績(ハードパワー)も大事ですが、人を惹きつける魅力(ソフトパワー)も忘れないことと思います。
人間は、一人ひとりが違う文化(価値)を持っています。違った文化を持つ人間が、ぶつかっても、受け入れる心の容量の大きさが人望と考えます。
そのような地域の先輩を目標して、日々私も自分を高めることに気を付けながら、人との交流を大事にして行きたいと思っています。
Posted by ノグチ(noguchi) at
13:00
│Comments(0)
2007年09月10日
西郷隆盛の魅力を考える「人望」
西郷隆盛の魅力を考える「人望」
本屋で見つけた「人望の研究」なる本を、時間が空いたときに少しづつ読んでいるが、なかなか読み、自分の行動を考えるのに、参考になる部分が多々ある。中身は、中国古典の人生訓を現代風に解説しているだけなのだが、古文を読むにはなかなか時間も調査も要るので、寸暇の休憩に読むには、現代語の方が入りやすいと思います。
相手の気持ちを考慮して、望むこといかにキャッチし、タイムリーに対応し、周りの方全てが心地良い気持ちを持ちながら、事が進むことを考え続ける姿勢が大事と説いています。なんだ、当たりまえのことではないかと思いますが、人間、その場になれば感情やそれまでの人間関係等々で、無心(私心を捨てる)に成れないが常と思います。
西郷隆盛の言葉「敬天愛人」は、「天を敬い、(全ての)人を愛する心」を現していますが、はたして西郷隆盛のように、毎日そんな気持ちを持ち続けることは、むずかしものと思います。
孔子の教えで最も重きを置いていた「仁」のこころは、相手を思いやる優しさであり、哀れみが基本にあります。井戸に落ちそうな子供を見た瞬間に、「どうにかしないと」と湧き出でる心もその一つです。困窮する人に思いを馳せる気持ちこそが、孔子の教育理念ではと私は思っています。西郷隆盛は、儒教の教えを大きく受けていると言われていますが、さらに人生の苦難中で、到達した自分を持っていたのだと思います。
人望=魅力、磁力は、日々の暮らしの中の言動に注意し、遭遇する苦難に向かい、前向きな心と優しさを、常に持ち続けることだと思います。
周りの出来事を「ゆるす(恕す)」懐の深さを育てて行きたいと思っています。
*参考資料:山崎武也著「人望力」
本屋で見つけた「人望の研究」なる本を、時間が空いたときに少しづつ読んでいるが、なかなか読み、自分の行動を考えるのに、参考になる部分が多々ある。中身は、中国古典の人生訓を現代風に解説しているだけなのだが、古文を読むにはなかなか時間も調査も要るので、寸暇の休憩に読むには、現代語の方が入りやすいと思います。
相手の気持ちを考慮して、望むこといかにキャッチし、タイムリーに対応し、周りの方全てが心地良い気持ちを持ちながら、事が進むことを考え続ける姿勢が大事と説いています。なんだ、当たりまえのことではないかと思いますが、人間、その場になれば感情やそれまでの人間関係等々で、無心(私心を捨てる)に成れないが常と思います。
西郷隆盛の言葉「敬天愛人」は、「天を敬い、(全ての)人を愛する心」を現していますが、はたして西郷隆盛のように、毎日そんな気持ちを持ち続けることは、むずかしものと思います。
孔子の教えで最も重きを置いていた「仁」のこころは、相手を思いやる優しさであり、哀れみが基本にあります。井戸に落ちそうな子供を見た瞬間に、「どうにかしないと」と湧き出でる心もその一つです。困窮する人に思いを馳せる気持ちこそが、孔子の教育理念ではと私は思っています。西郷隆盛は、儒教の教えを大きく受けていると言われていますが、さらに人生の苦難中で、到達した自分を持っていたのだと思います。
人望=魅力、磁力は、日々の暮らしの中の言動に注意し、遭遇する苦難に向かい、前向きな心と優しさを、常に持ち続けることだと思います。
周りの出来事を「ゆるす(恕す)」懐の深さを育てて行きたいと思っています。
*参考資料:山崎武也著「人望力」
Posted by ノグチ(noguchi) at
12:58
│Comments(2)
2007年09月10日
知るとは、知らないと素直に言えること(論語)
知るとは、知らないと素直に言えること(論語)
「子曰わく、由、女(なんじ)に之を知るをおし(教)えんか。之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為す。是れ知る為り」
(解説)
孔子先生が語られた「由よ、お前に『知る』ということをおしえようか。知っていることを知っている。知らないことを知らないと素直に言えるのが、本当に知るということだ」
(感想)
生半可の理解で人に語るときに、確信がないせいか説得力にかけることがあります。これは、理解していない性で、話題の流れの中で、話すときに気を付けなければいけないと思います。
孔子の「知らないことは、知らないと言えることが、本当に知ること。」の教示は、日頃の言動を検証する良き機会になりました。
「子曰わく、由、女(なんじ)に之を知るをおし(教)えんか。之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為す。是れ知る為り」
(解説)
孔子先生が語られた「由よ、お前に『知る』ということをおしえようか。知っていることを知っている。知らないことを知らないと素直に言えるのが、本当に知るということだ」
(感想)
生半可の理解で人に語るときに、確信がないせいか説得力にかけることがあります。これは、理解していない性で、話題の流れの中で、話すときに気を付けなければいけないと思います。
孔子の「知らないことは、知らないと言えることが、本当に知ること。」の教示は、日頃の言動を検証する良き機会になりました。
Posted by ノグチ(noguchi) at
07:58
│Comments(0)
2007年09月10日
思うて学ばざれば則ちあやうし
思うて学ばざれば則ちあやうし
「子曰わく、学びて思わざれば、則(すなわ)ちくらく、思うて学ばざれば則ちあやうし」
(解説)
孔子先生が語られた「学ぶだけで深く考えなければ、本当の意味がわからない。考えるのみで学ばなければ、独断におちいて危ない」
(感想)
理解(会得、悟り)まで、学び続けることが大事と先輩から良く指導を受けます。「ハッ」と気づくまで、地道の古典や偉人の言葉を学ぶことが重要と最近感じています。
「子曰わく、学びて思わざれば、則(すなわ)ちくらく、思うて学ばざれば則ちあやうし」
(解説)
孔子先生が語られた「学ぶだけで深く考えなければ、本当の意味がわからない。考えるのみで学ばなければ、独断におちいて危ない」
(感想)
理解(会得、悟り)まで、学び続けることが大事と先輩から良く指導を受けます。「ハッ」と気づくまで、地道の古典や偉人の言葉を学ぶことが重要と最近感じています。
Posted by ノグチ(noguchi) at
07:57
│Comments(0)
2007年09月09日
自他を見比べる、バランス感覚を (短文)
自他を見比べる、バランス感覚を (短文)
自他を見比べる、バランス感覚を(菜根譚)
人の境遇はさまざまであって、恵まれている者もいれば恵まれていない者もいる。それなのに、どうして自分一人だけすべての面で恵まれることを期待できようか。
自分の心の動きも様々であって、道理にかなっている場合もあればかなっていない場合もある。それなのに、どうしてすべての人々を道理に従わせることができようか。
自他を見比べながら、バランス感覚をはたらかせのも、処世の便法なのである。
(解説)
自分を中心に世の中を見ていると、どうしてもゆがんだ判断を形成し、はた迷惑な行動に走ってしまう。時には相手の立場になって考えてみたい。
(感想)
相手を思いやる気持ちを、忘れないことが大事と思います。自分がきつい時は、自分と同じ人は、世には沢山いることを忘れない。また、良い時こそが客観的に自分のおごりを検証することも忘れない。人は、人と関わり合ってこそ生きれると思うので、時々自分の行動をふり返り、反省し、また他の人々の行動にも関心を持ち、良きものは取り入れ、悪しきものは反面教師の材料にするゆとりが大事と思います。
時々自分を離れ、自分を見直す時間を持つことが必要と思いました。
自他を見比べる、バランス感覚を(菜根譚)
人の境遇はさまざまであって、恵まれている者もいれば恵まれていない者もいる。それなのに、どうして自分一人だけすべての面で恵まれることを期待できようか。
自分の心の動きも様々であって、道理にかなっている場合もあればかなっていない場合もある。それなのに、どうしてすべての人々を道理に従わせることができようか。
自他を見比べながら、バランス感覚をはたらかせのも、処世の便法なのである。
(解説)
自分を中心に世の中を見ていると、どうしてもゆがんだ判断を形成し、はた迷惑な行動に走ってしまう。時には相手の立場になって考えてみたい。
(感想)
相手を思いやる気持ちを、忘れないことが大事と思います。自分がきつい時は、自分と同じ人は、世には沢山いることを忘れない。また、良い時こそが客観的に自分のおごりを検証することも忘れない。人は、人と関わり合ってこそ生きれると思うので、時々自分の行動をふり返り、反省し、また他の人々の行動にも関心を持ち、良きものは取り入れ、悪しきものは反面教師の材料にするゆとりが大事と思います。
時々自分を離れ、自分を見直す時間を持つことが必要と思いました。
Posted by ノグチ(noguchi) at
18:55
│Comments(0)
2007年09月09日
人は何になるかではなくてどう生きるか
読んだ本や記事から、他
始めに私も尊敬している熊本在住の賢人である安永蕗子(ふきこ)先生が、熊本市国際交流会館の広報誌に寄稿されたものを読み感銘を受けました。これは、国際交流会館が「論語」の講座を開催し、そこで安永先生が講話をされた後の感想を述べられたものですが、世界情勢と論語の学ぶ意味も含めての文になっています。
その中で印象に残っている部分が、日本人は中国から文字を学び、学問をするようになった。安永先生の講義の冒頭で、「人は何になるかではなくてどう生きるか」と論語の解説が始まったそうです。学ぶ意味の本質がここにあるように思います。
・諸橋徹治選書「孟子の話し」
孟子の教えを解説を入れてまとめてある本ですが、いくつか印象に残ることがありました。教育、育英は、孟子が始めて使われた言葉として紹介されています。
①仁は人の心なり、義は人の道なり
私心を捨てて(放心)考え出すものが、人を敬愛するやさしさを「仁」。私心をすてた心で、人のために行動を起こすことを「義」
②天地の間で、浩然の気以上に大きく強いものはない
浩然の気とは、
「義」すなわち人間の心の中の正義、
「道」すなわち天地の自然の道理を合わせた気持ち(理念)。
浩然の気を義と道とのわけると、「義」は長い間本人自身が自分の心の中で育み、合わせ集めて、そこから自然に生じた内部的な輝きである。重要なことは、一時も忘れてはならない。
・PHP三月号から
①「人生を未知と感じ、おおいに恐れ、おおいに期待し、しらけずにつき進む姿を情熱と呼ぶ。」(阿久悠語録)
・ペリクレス演説抜粋(BC.431)
(中略)・・我々は、素朴なる美を愛し、柔弱に堕することなき知をあいしする。我々は、富を行動の礎とするが、いたずらに富を誇らない。また身の貧しさを認めることを恥としないが、貧困を克服する努力を怠ることを深く恥じる。そして己れの家計同様に国の計にもよく心を用い、己の生業に熟練をはげむかたわら、国(地域)の進むべき道に充分な判断をもつように心得る。ただわれら のみは、公私領域の活動に関与せぬものを閑を楽しむとは言わず、ただ無益な 人間と見なす。・・(中略)
紀元前のギリシャのリーダーの演説ですが、今の市民はこの指摘を実行できているでしょうか?日本は、経済成長に走りすぎて人の生き方(学問)の勧めが薄れていると感じます。それぞれの幸福が実現できる時代になればと願います。
初めの安永先生の言葉ですが「学問は、どう生きるか、を知ることである」と「人は何になるかではなくてどう生きるか」とあります。日常のことに流されず、常に志を高く持ち、行動することが大事なようです。
始めに私も尊敬している熊本在住の賢人である安永蕗子(ふきこ)先生が、熊本市国際交流会館の広報誌に寄稿されたものを読み感銘を受けました。これは、国際交流会館が「論語」の講座を開催し、そこで安永先生が講話をされた後の感想を述べられたものですが、世界情勢と論語の学ぶ意味も含めての文になっています。
その中で印象に残っている部分が、日本人は中国から文字を学び、学問をするようになった。安永先生の講義の冒頭で、「人は何になるかではなくてどう生きるか」と論語の解説が始まったそうです。学ぶ意味の本質がここにあるように思います。
・諸橋徹治選書「孟子の話し」
孟子の教えを解説を入れてまとめてある本ですが、いくつか印象に残ることがありました。教育、育英は、孟子が始めて使われた言葉として紹介されています。
①仁は人の心なり、義は人の道なり
私心を捨てて(放心)考え出すものが、人を敬愛するやさしさを「仁」。私心をすてた心で、人のために行動を起こすことを「義」
②天地の間で、浩然の気以上に大きく強いものはない
浩然の気とは、
「義」すなわち人間の心の中の正義、
「道」すなわち天地の自然の道理を合わせた気持ち(理念)。
浩然の気を義と道とのわけると、「義」は長い間本人自身が自分の心の中で育み、合わせ集めて、そこから自然に生じた内部的な輝きである。重要なことは、一時も忘れてはならない。
・PHP三月号から
①「人生を未知と感じ、おおいに恐れ、おおいに期待し、しらけずにつき進む姿を情熱と呼ぶ。」(阿久悠語録)
・ペリクレス演説抜粋(BC.431)
(中略)・・我々は、素朴なる美を愛し、柔弱に堕することなき知をあいしする。我々は、富を行動の礎とするが、いたずらに富を誇らない。また身の貧しさを認めることを恥としないが、貧困を克服する努力を怠ることを深く恥じる。そして己れの家計同様に国の計にもよく心を用い、己の生業に熟練をはげむかたわら、国(地域)の進むべき道に充分な判断をもつように心得る。ただわれら のみは、公私領域の活動に関与せぬものを閑を楽しむとは言わず、ただ無益な 人間と見なす。・・(中略)
紀元前のギリシャのリーダーの演説ですが、今の市民はこの指摘を実行できているでしょうか?日本は、経済成長に走りすぎて人の生き方(学問)の勧めが薄れていると感じます。それぞれの幸福が実現できる時代になればと願います。
初めの安永先生の言葉ですが「学問は、どう生きるか、を知ることである」と「人は何になるかではなくてどう生きるか」とあります。日常のことに流されず、常に志を高く持ち、行動することが大事なようです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
18:42
│Comments(0)
2007年09月09日
知識には、「知識、見識、胆識」あり
知識には、「知識、見識、胆識」あり
先哲の智恵① 知識には「知識、見識、胆識」あり
江戸期の名著に「水雲問答」と言う儒学者と高名な藩主との手紙を使った質疑回答をまとめたものがあります。リーダーの信念と徳をどう培っていくかには、現代でも充分参考になる名著と思います。その中に一節にあるものを紹介します。
(訳文より)
・・「識」には三つある。一つは、「知識」で、これは一番つまらん。雑識と言ますけど、今日で言うとディレッタントというもの、これはあまり値打ちがない。人間には単なる知識ではなく「見識」、価値判断が大事である。見識がなければ語るに足らん。ところが見識があっても、どうかすると、その人が臆病である、あるいは狡猾である、軽薄であるというと、その見識も役に立たん。いかなる抵抗があっても、いかなる困難に臨んでも、確信するところ、徹見するとことを敢然(かんぜん)として断行し得るような実行力・度胸を伴った知識・見識を「胆識」と言う。見識があっても胆識がない人はたくさんいる。しかし人間は、胆識があってはじめて本当の知識人である。これは東洋の知識学というものの根本問題であります。・・・(安岡正篤著、「先哲が説く指導者の条件」より)
(感想)
色々な会議に参加することがあるのですが、会議の後になって「あのことは、こう思ったのだが・・・」「自分は、こうしたいと・・」と中心人物や、問題発言の人に、意見を言う人が居ますが、これこそ「見識あって、胆識無し」の知識人と思います。
公の場で、手を上げて静まった空気の中で、自分の意見を述べる「胆」の座った知識を持ちたいものです。
会議後のロビー活動でなく、自分の意見を述べるために、会議前のロビー活動方が、効果も信用も生まれると思います。
重要な会議には、少しでも早く会議場に到着し、主要な人物と雑談し、空気を読み自分の意見を真摯に聞いてくれる雰囲気作りも大事と思います。後は、会議での情報を真剣に識見し、思いのたけを勇気を持って意見を言う訓練を積み重ねる試みを続けると良いと感じます。感想が長くなりました。
「知識」「見識(識見)」「胆識」の言葉を心に持ちつつ、人の話しに耳を傾けたいと思います。
先哲の智恵① 知識には「知識、見識、胆識」あり
江戸期の名著に「水雲問答」と言う儒学者と高名な藩主との手紙を使った質疑回答をまとめたものがあります。リーダーの信念と徳をどう培っていくかには、現代でも充分参考になる名著と思います。その中に一節にあるものを紹介します。
(訳文より)
・・「識」には三つある。一つは、「知識」で、これは一番つまらん。雑識と言ますけど、今日で言うとディレッタントというもの、これはあまり値打ちがない。人間には単なる知識ではなく「見識」、価値判断が大事である。見識がなければ語るに足らん。ところが見識があっても、どうかすると、その人が臆病である、あるいは狡猾である、軽薄であるというと、その見識も役に立たん。いかなる抵抗があっても、いかなる困難に臨んでも、確信するところ、徹見するとことを敢然(かんぜん)として断行し得るような実行力・度胸を伴った知識・見識を「胆識」と言う。見識があっても胆識がない人はたくさんいる。しかし人間は、胆識があってはじめて本当の知識人である。これは東洋の知識学というものの根本問題であります。・・・(安岡正篤著、「先哲が説く指導者の条件」より)
(感想)
色々な会議に参加することがあるのですが、会議の後になって「あのことは、こう思ったのだが・・・」「自分は、こうしたいと・・」と中心人物や、問題発言の人に、意見を言う人が居ますが、これこそ「見識あって、胆識無し」の知識人と思います。
公の場で、手を上げて静まった空気の中で、自分の意見を述べる「胆」の座った知識を持ちたいものです。
会議後のロビー活動でなく、自分の意見を述べるために、会議前のロビー活動方が、効果も信用も生まれると思います。
重要な会議には、少しでも早く会議場に到着し、主要な人物と雑談し、空気を読み自分の意見を真摯に聞いてくれる雰囲気作りも大事と思います。後は、会議での情報を真剣に識見し、思いのたけを勇気を持って意見を言う訓練を積み重ねる試みを続けると良いと感じます。感想が長くなりました。
「知識」「見識(識見)」「胆識」の言葉を心に持ちつつ、人の話しに耳を傾けたいと思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
18:34
│Comments(0)
2007年09月09日
自分の心に勝つ (克己心)
自分の心に勝つ (克己心)
まず自分の心に打ち勝とう。そうすれば、あらゆる煩悩を退散させることができる。
まず自分の気持ちを平静にしよう。そうすれば、あらゆる誘惑から身を守ることができる。
(解説)
人に勝つのはやさしいが、自分に勝つのはむずかしいとされる。明代の思想家王陽明も、「山中ノ賊ヲ破ルハ易(ヤス)ク、心中ノ賊ヲ破ルハ難(カタ)シ」と喝破しているように、自分の心に勝つといっても容易ではないのである。
自分に勝つことのできる人こそ強者なのかもしれない。要は、そのための努力を怠ってはならないということである。
西郷隆盛の遺訓に、「おのれに克つ」の一説に、
(本文より)
人が知るべき道は、「天地自然」の道です。天地自然の道を知るためには「敬天愛人」を目的として学び続けることです。
天を敬う。
人を愛する。
自分の欲や拘りは、この二つの精神を越えては、けっしていけない。欲や拘りをゼロにせよ、と言うているのでない。「敬天愛人」の精神よりも肥大させてはいけない、と言うのである。
人は、自分を愛しすぎると、「敬天愛人」の精神を忘れてしまうものです。それが大きな誤りの第一歩となります。
そのためには、ふだんから学び続ける中で、常に「克己」を心がけることです。
「克己」、すなわちおのれに克つ。・・(中略)
日常の修養こそが、このおのれに克つ「心」を育て続けると先人が言っているのですが、菜根譚ような生きるための訓示をいつも読むことで、緩んだ心を道に、揺り戻すことができのだと思います。
安岡正篤先生の「心読」の言葉が表わすように、知識は体現してこそ本物なのかもしれません。
*参考資料:西郷南州遺訓~無事は有事のごとく、有事は無事のごとく~
まず自分の心に打ち勝とう。そうすれば、あらゆる煩悩を退散させることができる。
まず自分の気持ちを平静にしよう。そうすれば、あらゆる誘惑から身を守ることができる。
(解説)
人に勝つのはやさしいが、自分に勝つのはむずかしいとされる。明代の思想家王陽明も、「山中ノ賊ヲ破ルハ易(ヤス)ク、心中ノ賊ヲ破ルハ難(カタ)シ」と喝破しているように、自分の心に勝つといっても容易ではないのである。
自分に勝つことのできる人こそ強者なのかもしれない。要は、そのための努力を怠ってはならないということである。
西郷隆盛の遺訓に、「おのれに克つ」の一説に、
(本文より)
人が知るべき道は、「天地自然」の道です。天地自然の道を知るためには「敬天愛人」を目的として学び続けることです。
天を敬う。
人を愛する。
自分の欲や拘りは、この二つの精神を越えては、けっしていけない。欲や拘りをゼロにせよ、と言うているのでない。「敬天愛人」の精神よりも肥大させてはいけない、と言うのである。
人は、自分を愛しすぎると、「敬天愛人」の精神を忘れてしまうものです。それが大きな誤りの第一歩となります。
そのためには、ふだんから学び続ける中で、常に「克己」を心がけることです。
「克己」、すなわちおのれに克つ。・・(中略)
日常の修養こそが、このおのれに克つ「心」を育て続けると先人が言っているのですが、菜根譚ような生きるための訓示をいつも読むことで、緩んだ心を道に、揺り戻すことができのだと思います。
安岡正篤先生の「心読」の言葉が表わすように、知識は体現してこそ本物なのかもしれません。
*参考資料:西郷南州遺訓~無事は有事のごとく、有事は無事のごとく~
Posted by ノグチ(noguchi) at
09:04
│Comments(0)
2007年09月09日
君子は周して比せず
君子は周して比せず
「子曰わく、君子は周して比せず、小人は比して周せず」
(解説)
孔子先生が語れた「君子は、誰とでも公平に親しみ、ある特定の人とかたよって交わらない。小人は、かたよって交わるが、誰とでも親しく公平に交わらない」
(感想)
○○派、○○会等、派閥やグループを直ぐ作るのが、日本人ですが、他を排除しないのであればなかなか、気骨のある集まりになりりますが、仲良しこよしの集まりでは、対立が生じてくるのは、致し方ないものです。
君子は、かたよらず、徒党を組まず、広く交友を持つことが重要と思います。君子の交友は「淡交(友)」とも言いますが、べったりの友好関係は、壊れると怨みなり、かえって難しいように思います。「君子は周して比せず」を心がけたいと思います。
「子曰わく、君子は周して比せず、小人は比して周せず」
(解説)
孔子先生が語れた「君子は、誰とでも公平に親しみ、ある特定の人とかたよって交わらない。小人は、かたよって交わるが、誰とでも親しく公平に交わらない」
(感想)
○○派、○○会等、派閥やグループを直ぐ作るのが、日本人ですが、他を排除しないのであればなかなか、気骨のある集まりになりりますが、仲良しこよしの集まりでは、対立が生じてくるのは、致し方ないものです。
君子は、かたよらず、徒党を組まず、広く交友を持つことが重要と思います。君子の交友は「淡交(友)」とも言いますが、べったりの友好関係は、壊れると怨みなり、かえって難しいように思います。「君子は周して比せず」を心がけたいと思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
09:02
│Comments(0)
2007年09月07日
君子は、器ならず
君子は、器ならず
「子曰わく、君子は器ならず」
(解説)
孔子先生が語られた「できた人物は、特定のはたらきを持った器のようでない」
(感想)
動物界では、自分を大きく見せようと求愛ダンスをする種もいますが、人間界にもたまに見えます。
今日も、ある県議から質問を見に来てくださいと案内の葉書が来ていました。このようなものは、質問内容がよければ自ずと、うわさは広がるものです。
宣伝ばかりの目だった、議員の質を問う風潮が広がらないのがとても残念です。「君子の道は身を修むるに有り」と説いています。ぜひ、現代の政治家のその理念を学んで欲しいと願うばかりです。
「子曰わく、君子は器ならず」
(解説)
孔子先生が語られた「できた人物は、特定のはたらきを持った器のようでない」
(感想)
動物界では、自分を大きく見せようと求愛ダンスをする種もいますが、人間界にもたまに見えます。
今日も、ある県議から質問を見に来てくださいと案内の葉書が来ていました。このようなものは、質問内容がよければ自ずと、うわさは広がるものです。
宣伝ばかりの目だった、議員の質を問う風潮が広がらないのがとても残念です。「君子の道は身を修むるに有り」と説いています。ぜひ、現代の政治家のその理念を学んで欲しいと願うばかりです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
22:51
│Comments(0)
2007年09月07日
烈士暮年、壮心已まず
烈士暮年、壮心已まず
「少年老いやすく学成りがたし」と、人生の短さと学問の学びのむずかしさを表現した言葉ですが、今日の表題の「烈士暮年、壮心已まず」は、『三国志』の魏の曹操が晩年詠んだ詩です。
小説三国志の中で曹操は、、悪役になっていますが、実際の曹操は、戦が強かったこだけでなく、学問も教養も身につけた人で、とても勉強熱心だったと、実際の三国志には書かれています。遠征に行くのにも、常に数冊の古典を持って行って、敵と対戦中でも暇を見つけて目を通したそうで、晩年になっても本を手元から離さなかったそうです。
曹操は、詩人でもあって表題の漢詩は、晩年読んだ詩と言われています。詩の意味は、
烈士:男らしい男
暮年:晩年の意味
壮心:若々しい心、チャレンジ精神
この詩は、曹操自身「こうありたい」と願って詠んだ一句であると思います。曹操の生涯のテーマだったのかもしれません。(守屋洋著、三国志名言参照)
人は、心の持ちようで「若さ」が保てると、何人もの先輩から聞きました。常にチャレンジ精神を持ち続けるのは難しいことで、先人たちの生き様に学ぶことが重要と、中国の英雄たちも同様に先人の偉業を学んでいたことを知り、深く感銘を受けます。
「憲政の神様」尾崎行雄氏、75歳の時に語った言葉「人生の本舞台は、将来に在り」の言葉を思い出します。日本の偉人たちも、多くの経験と書を読み、悩みながら人生を歩んだのだと思います。
今の日本の「不透明感」を打開するのは、一人ひとりのチャレンジ精神の高揚ではないかと思います。 いつまでも壮心をもち続けたいと思います。
私の師の一人、内田健三先生の言葉を最後に今日の日記終わりたいと思います。
「人は年を追うごとに体力は落ちていくが、精神は何処まででも成長する」
「少年老いやすく学成りがたし」と、人生の短さと学問の学びのむずかしさを表現した言葉ですが、今日の表題の「烈士暮年、壮心已まず」は、『三国志』の魏の曹操が晩年詠んだ詩です。
小説三国志の中で曹操は、、悪役になっていますが、実際の曹操は、戦が強かったこだけでなく、学問も教養も身につけた人で、とても勉強熱心だったと、実際の三国志には書かれています。遠征に行くのにも、常に数冊の古典を持って行って、敵と対戦中でも暇を見つけて目を通したそうで、晩年になっても本を手元から離さなかったそうです。
曹操は、詩人でもあって表題の漢詩は、晩年読んだ詩と言われています。詩の意味は、
烈士:男らしい男
暮年:晩年の意味
壮心:若々しい心、チャレンジ精神
この詩は、曹操自身「こうありたい」と願って詠んだ一句であると思います。曹操の生涯のテーマだったのかもしれません。(守屋洋著、三国志名言参照)
人は、心の持ちようで「若さ」が保てると、何人もの先輩から聞きました。常にチャレンジ精神を持ち続けるのは難しいことで、先人たちの生き様に学ぶことが重要と、中国の英雄たちも同様に先人の偉業を学んでいたことを知り、深く感銘を受けます。
「憲政の神様」尾崎行雄氏、75歳の時に語った言葉「人生の本舞台は、将来に在り」の言葉を思い出します。日本の偉人たちも、多くの経験と書を読み、悩みながら人生を歩んだのだと思います。
今の日本の「不透明感」を打開するのは、一人ひとりのチャレンジ精神の高揚ではないかと思います。 いつまでも壮心をもち続けたいと思います。
私の師の一人、内田健三先生の言葉を最後に今日の日記終わりたいと思います。
「人は年を追うごとに体力は落ちていくが、精神は何処まででも成長する」
Posted by ノグチ(noguchi) at
10:24
│Comments(0)
2007年09月07日
やる気があれば進歩する
やる気があれば進歩する
(意訳)
手のおえない暴れ馬のも、慣らし方ひとつで乗りこなせる。鋳型からとびはねた金も、いずれは型におさまる。人間も、やる気のある人間はまだいい。始末のわるいのは、のらくらしているやる気のない連中だ。こんな手合いはいつまでたっても進歩が望めない。
白沙先生も語っている。「人間として欠点が多いのは恥ずべき子ことではない。むしろ欠点のない人間のほうが案じられる」と。これは、達見だと思う。
(守屋洋先生の注釈)
孔子も、「一日中食べることばかり考えて頭を使おうとしない連中は、どうしようもない。」(論語)と語っている。なんでもいいから、やる気を出してチャレンジしたい。
(感想)
いつも、ワクワクしながら明日何をやろうと思うだけでも元気なるものです。
例えば、旅に行くまで色々計画し、準備する楽しさは、旅は3度楽しめると言われることと思います。
始める前に言い訳を作り、日常の連続から抜け出せず、同じことを続けるよりは、新しい試みに挑戦し、苦労をする方が楽しい人生と思えるのは、私だけではないと思います。
*今日は、守屋洋著「新釈 菜根譚」より、心に残った言葉を紹介しました。ご意見頂ければ幸いです。
(意訳)
手のおえない暴れ馬のも、慣らし方ひとつで乗りこなせる。鋳型からとびはねた金も、いずれは型におさまる。人間も、やる気のある人間はまだいい。始末のわるいのは、のらくらしているやる気のない連中だ。こんな手合いはいつまでたっても進歩が望めない。
白沙先生も語っている。「人間として欠点が多いのは恥ずべき子ことではない。むしろ欠点のない人間のほうが案じられる」と。これは、達見だと思う。
(守屋洋先生の注釈)
孔子も、「一日中食べることばかり考えて頭を使おうとしない連中は、どうしようもない。」(論語)と語っている。なんでもいいから、やる気を出してチャレンジしたい。
(感想)
いつも、ワクワクしながら明日何をやろうと思うだけでも元気なるものです。
例えば、旅に行くまで色々計画し、準備する楽しさは、旅は3度楽しめると言われることと思います。
始める前に言い訳を作り、日常の連続から抜け出せず、同じことを続けるよりは、新しい試みに挑戦し、苦労をする方が楽しい人生と思えるのは、私だけではないと思います。
*今日は、守屋洋著「新釈 菜根譚」より、心に残った言葉を紹介しました。ご意見頂ければ幸いです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
10:09
│Comments(0)
2007年09月07日
人の過ちは、仲間や心がけから出る
人の過ちは、仲間や心がけから出る
「子曰わく、人の過ちや、各々其の党に於いてす。過ちを観(み)てここに仁を知る」
(解説)
孔子先生が語られた、「人の過ちは、それぞれの仲間や心がけから出るものである。従って過ちの内容を見て、その人の仁、不仁がわかるものだ」
(感想)
孔子の最も重要な教えの一つ「仁」の心は、仲間や日常の心がけ(行い)を見れば、自ずと解かるという言葉に、ドキッとするものが有りますが、幕末の偉人、横井小楠の訓示に、「君子の道は身を修むるに有り」とあるように、大志を抱き行動起すことも大事ですが、その信用(支持)はそれまでの日常の言動によることが多々あるものです。
仁の心を育てることが先ず大事と、孔子は説いているだと思います。仁とは、哀れむとか、思いやりの心とかの意味と言われます。家族にしろ、仲間にしろ、「彼らって、良いよね」と言われるようになりたいものです。
「子曰わく、人の過ちや、各々其の党に於いてす。過ちを観(み)てここに仁を知る」
(解説)
孔子先生が語られた、「人の過ちは、それぞれの仲間や心がけから出るものである。従って過ちの内容を見て、その人の仁、不仁がわかるものだ」
(感想)
孔子の最も重要な教えの一つ「仁」の心は、仲間や日常の心がけ(行い)を見れば、自ずと解かるという言葉に、ドキッとするものが有りますが、幕末の偉人、横井小楠の訓示に、「君子の道は身を修むるに有り」とあるように、大志を抱き行動起すことも大事ですが、その信用(支持)はそれまでの日常の言動によることが多々あるものです。
仁の心を育てることが先ず大事と、孔子は説いているだと思います。仁とは、哀れむとか、思いやりの心とかの意味と言われます。家族にしろ、仲間にしろ、「彼らって、良いよね」と言われるようになりたいものです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
07:47
│Comments(0)
2007年09月06日
自分を決してかくせるものではない
自分を決してかくせるものではない
「子曰く、其の以(な)す所を視(み)、其の由る所を観(み)、其の安(やす)んずる所を察(み)れば、人いずくんぞかく(隠)さんや。人いずくんぞかく(隠)さんや。」
(解説)
孔子先生は語れた「その人が何をしているのか、その人が何によって行っているのか、そしてその人がどこに安らぎをもっているのか。そういうことを観察すれば、人の値打ちはわかるものだ。
従って自分をかくそうと思っていも、決してかくせるものではない」
(感想)
故事に、人知れず「賄賂」を送ろうと、夜に自宅へ出かけた人が、官僚に向かい「二人だけしか、知りませんから」と、差し出すと、受けての人は「私もあなたも知っていて、天も知っている」から、私は受け取らないと拒否した話を思い出します。
一人で居ても、曲がってことは決してしないことが、真っ当の自信になると感じます。最近の政治スキャンダル、「天は、必ず見ている」と言う緊張感を持って欲しいものです。
「子曰く、其の以(な)す所を視(み)、其の由る所を観(み)、其の安(やす)んずる所を察(み)れば、人いずくんぞかく(隠)さんや。人いずくんぞかく(隠)さんや。」
(解説)
孔子先生は語れた「その人が何をしているのか、その人が何によって行っているのか、そしてその人がどこに安らぎをもっているのか。そういうことを観察すれば、人の値打ちはわかるものだ。
従って自分をかくそうと思っていも、決してかくせるものではない」
(感想)
故事に、人知れず「賄賂」を送ろうと、夜に自宅へ出かけた人が、官僚に向かい「二人だけしか、知りませんから」と、差し出すと、受けての人は「私もあなたも知っていて、天も知っている」から、私は受け取らないと拒否した話を思い出します。
一人で居ても、曲がってことは決してしないことが、真っ当の自信になると感じます。最近の政治スキャンダル、「天は、必ず見ている」と言う緊張感を持って欲しいものです。
Posted by ノグチ(noguchi) at
23:48
│Comments(0)